メルボルンのクッカリーに通う学生の日常week7
先週、ある一通のメールが届きました。
政府からのメール。
学生ビザがようやく降りたことを告げるメールでした。
申請自体は2ヶ月くらい前にしていて、学校もすでに始まってましたが、ようやく降りました。
おそらくオーストラリアあるあるです。
これであと2年間オーストラリアにいれることが確定しました。
学生ビザが降りたということは、オーストラリアのワーホリビザが終了したということでした。
人生2回目のワーホリビザが終了しました。
自分は、1ヵ国目のワーホリでカナダのトロント、そしてキャンモアという街で生活をしました。
そして2カ国目のワーホリでオーストラリアのメルボルンに来ました。
その後、色々あってあっという間に1年が経ちました。
2回目のワーホリを終えての率直な感想は、
「ワーホリを2カ国経験することは正解」ということです。
….。
なんの説得力もないです。
ワーホリなど所詮遊び。
1年間で十分。
2年間もするものではない。
現実逃避の延長でしかない。
そう考えたあなた。
分かります。
ですが、2回目のワーホリだからこそ経験できることもあります。
✅ワーホリに少しでも興味があるあなた
✅なんとなく人生の帰路に立っているあなた
今回の記事が一つの経験談として、どなたかの参考になれば幸いです。
【経験談】2回目のワーホリだからこそ経験できたこと(カナダ・オーストラリア)
英語力の伸びは尻上がり

まず英語力に関して、1年目の伸びと2年目の伸びを比べると圧倒的に2年目の方が伸び率が大きかったと感じます。
まさに指数関数的に伸びた気がします。
特に自分の場合は、この一年でスピーキングがかなりレベルアップしました。
使える表現や語彙力は1年目よりもかなり増えました。
わからない表現を調べてメモしたり、映画で出てきた表現をメモしたりとコツコツやっていく中で伸びた気がします。
1年で帰国していては、確実に今のレベルにはなれていなかったと思うと残ってよかったなと思います。
スピーキングに関して、これは個人的な意見ですが、環境が変わる毎に伸びを実感しました。
仕事先を変えた時、住む街を変えた時など、新しい環境で新しい人たちと出会って会話をした時に、「あれ、こんな喋れたっけ」と伸びを実感していました。
おそらく、一度話してきた内容(日本の話、趣味の話など)をまた話す機会が増えるので、1度目よりも2度目の方が上手く話せるという原理だと思います。
重要なのは、自分の伸びを実感することです。
伸びを実感すると自信に繋がります。
自信がつくと、さらに話しやすくなります。
この好循環が非常に重要です。
そういう意味では、同じ2年でも同じ国で同じ職場で同じ人間関係で生活するより、国を変え、生活を変え、出会う人を増やした方が絶対に伸びやすいです。
2カ国目のワーホリを経験して得た一つのスキルかなと思います。
1年でペラペラで帰国できる人は、おそらく元々かなり話せる方か天才だけです。
語学学校通って、卒業したら仕事しながら英語レベルアップさせたいな。
みたいな方が、1年で自分が思い描くレベルまで英語力を伸ばすのはかなり困難だと思います。
自分もそうでした。
1年で字幕なしで洋画を見れるようになりたいなと思っていましたが、語学学校通って3ヶ月でこれは無理だと実感しました。
そんなものです。
なので、自分の求める英語力にもよりますが、多くの方が目指す海外旅行行って現地の方と自信を持ってコミュニケーション取れるレベルになる確率は、1年間より2年間の方が圧倒的に高いです。
この伸び期を経験しないのはもったいないです。
以上の理由から、英語を伸ばすことを第一目標にしている方は、1年で帰国するのは個人的にもったいないと思います。
2つで比べるより3つで比べた方がそりゃいい

自分が一番好きなラーメンの味を決めるとします。
塩ラーメンしか食べたことない人は、比べることができません。
塩味が好きな人はそれで満足するかもしれません。
しかし塩味が苦手な人は、ひとくくりにラーメンが苦手と言い出すかもしれません。
ある日、味噌ラーメンに出会います。
ここで初めて比べることができます。
自分は味噌の方が好きだな、逆に自分はやっぱり塩だななどと視野が広がります。
ここでさらに、世の中には豚骨ラーメンというものがあると聞いた時、あなたはどう思いますか。
新たな味を挑戦したくなりませんか。
この例えほど単純ではありませんが、ワーホリの2カ国目を挑戦するということは言わばそういうことです。
同じ海外とはいえ、文化や生活は全く違います。
新たな発見の連続です。
自分は今、日本、カナダ、オーストラリアという3つの生活の比較ができます。
だからこそわかるオーストラリアの良し悪しがあると思っています。
例えば、物価について、オーストラリアの物価は高いとよく言いますが、生活用品や食材は絶対カナダの方が高いです。
しかも、カナダは基本税抜き表示で、買った時にすごく損した気持ちになりましたが、オーストラリアはちゃんと税込表示で、全然カナダより安いやんと思った記憶があります。
アジアの食材もカナダより買いやすいし、日本との時差も少ないです。
などなど、カナダの生活を知っているからこそ「オーストラリアいいやん」となっている自分がいます。
逆にカナダの生活を知らなかったら、ここまでオーストラリアを好きになれていたかは分かりません。
2つで比べるより3つで比べた方が絶対いいです。
日本ともう一カ国で十分と思っているそこのあなた。
甘いです。
もう一カ国行きましょう。
初めての海外生活で自分のこと日本のことがよくわかったように、二カ国の海外生活でようやく見えてくることが必ずあります。
英語の上達はやっぱり嬉しいな。
初海外(ワーホリ)の自分は何かと本当に焦っていたな。
海外生活の楽しみ方ってこういうことか。
などなど。
以上の理由から、海外生活をする理由が自分の視野を広げたいだとか価値観を変えたいという方には、二カ国ワーホリは向いていると思います。
補足ですが、複数の国の生活体験をするなら世界一周のようなアドレスホッパーの方がいいのではないかと思う人もいるかもしれません。
もちろんそれもありですが、短期生活と長期生活は良くも悪くも全く違います。
長期生活だからこそ、見える景色があります。
何よりアラサーになると、そろそろ落ち着きたいという思いが必ず出てきます。
そこで、頻繁に家を変えて旅するのは正直自分にはしんどいかったです。
人間関係こそ海外生活を楽しむ原点にして頂点

個人的に、アラサーが海外生活を楽しめるかどうかは、よい人間関係を作れるかどうかで決まると思います。
仲のいい友達・パートナーが現地でできるかどうかが全てです。
国や街は正直そこまで重要でない気がします。
自分はカナダのトロント、キャンモア、そしてオーストラリアのメルボルンと計3つの街で生活してしました。
街の雰囲気の違い、娯楽の違いなど色々ありますが、結局一番楽しいのは、友達と遊んだり飲んだりする時です。
これは、日本でも海外でも同じです。
海外で楽しそうにしている人は決まってパートナーがいたり、友達が多いです。
逆に楽しめていない人は、家で一人で過ごす時間が多い傾向にあるように思います。
では、どうすれば良い人間関係が作れるかというと結局、英語力です。
カナダの語学学校に言っていた時、クラスメイトと必死に会話しようとしていましたが、自分の実力不足で相手が何を言っているかわからず、会話が続かない、沈黙が辛いなんてことがよくありました。
当然密な関係などできません。
必然的に帰り道を一人で帰るようになる。
一人の時間が増える。
海外生活楽しくない。
負のスパイラルの完成です。
人間は一人では生きていけない。
海外にいると日本以上に友達の重要さに気づきます。
この焼肉屋の焼肉のタレほど大事な英語力は、前述した通り1年間より2年間の海外生活の方が圧倒的に身につきます。
つまり、1年目より2年目の方がより良い人間関係は形成できる。
海外生活をもっと楽しいと思える。
自分はそう思います。
英語力の他にも、自分の知らなかった海外の習慣や音楽などの知識もつき、話題も豊富になります。
来た当初は、好きな音楽や趣味が全く合わず、全然共感できませんでしたが、今ではそう言ったことも少なくなりました。
このように「1年」という時間は、世の中の偉い人が便宜上決めた区切りにすぎません。
その区切りに縛られ、海外生活を終えてしまうのは、作ったその日のカレーを食べて満足するようなものです。
1日置いたカレーの方が熟して美味しいように、時間をかけてこそ本当の海外生活の楽しさを実感できると思います。
まとめ
以上、大まかに自分が感じた2回目のワーホリだからこそ経験できたことについて共有しました。
繰り返しますが、「ワーホリを2カ国経験することは正解」です。
なぜなら、1年目よりはるかに充実した海外生活を送れる可能性が高いからです。
オーストラリアに来た当初、ワーホリに来たばかりの日本人と会う機会がありました。
その不安そうな様子を見た時、1年前の自分と重なり「きっと大丈夫」と言いたくなりました。
そんなことを思っていた1年前の自分を、今思うと「自分の心配しろ」と言いたくなります。
それくらい1年間の成長はまだまだな気がします。
一方で、2年間ワーホリをすることのデメリットもあります。
先日、海外生活が長くなることで、日本の友達と価値観のずれが大きくなっているという話を聞きました。
仕方ないことですが、もうあの頃のような関係にはなれないと感じたとその子は言っていました。
海外生活が長くなると、日本の生活や人間関係が一変するということがあるようです。
仕方ないですが、確かに少し悲しい気もします。
最後に

この前、かまいたちととろサーモンのマネージャーをしていた樺澤さんが吉本を退社して憧れの海外生活を始めるというニュースを見ました。
YouTubeでよく見ていたし、順風満帆な人生のように動画では見えたので、それを投げ捨てて海外生活を選んだことに驚きました。
しかもオーストラリアワーホリのようでした。
その勇気を尊敬すると同時に、日本から見る海外生活の魅力はすごいのだろうなと改めて思いました。
自由。
英語を堪能に話す自分。
外国人のパートナーができる自分。
誰もが夢見る理想の海外です。
自分も海外への憧れは大学生の頃からあって、いつかはと思っていました。
だから、樺澤さんの決断に共感を覚えました。
しかし、いざアラサーで海外生活を始めると、英語力、仕事、人間関係など悩みや不安が尽きませんでした。
憧れの海外生活は、楽しみよりネガティブ感情の連続。
これが現実でした。
今でこそいい経験だったと思えますが、実際はかなり大変でした。
それが、今2年間の海外生活を終え、ようやく海外生活に地に足がついてきたと感じます。
英語力、仕事の目標、海外の友達。
1年目のカナダでのそれは、1年目相応のもので薄っぺらいベニヤ板でした。
今の方が、どれも洗練され、少しはましになったと言えます。
これだけでも、2年間ワーホリをしてよかったと思います。
・今の自分に納得がいっていないあなた
・ワーホリに少しでも興味があるあなた
・なんとなく人生の帰路に立っているあなた
この記事を読んで、海外に残るか迷っている人の背中を押せれば幸いです。
・
・
・
・
・
これからも自分の海外生活は続きます。
2年間の学生オーストラリア生活。
自分がどう変化していくのか。
今から楽しみです。
自分に期待はしないが、死ぬ間際にいい人生だったと思えるようにこれからも生きていきたい。
いざ30代。
まだまだこれからだ。
・
・
・
・
・
最後まで、ご清覧ありがとうございました。
現在は、メルボルンのクッカリーで料理の学習をしています。
そこに至った経緯なども良ければご覧ください。
では、また。
Hiromu
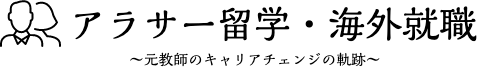




コメント